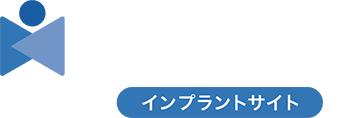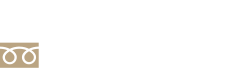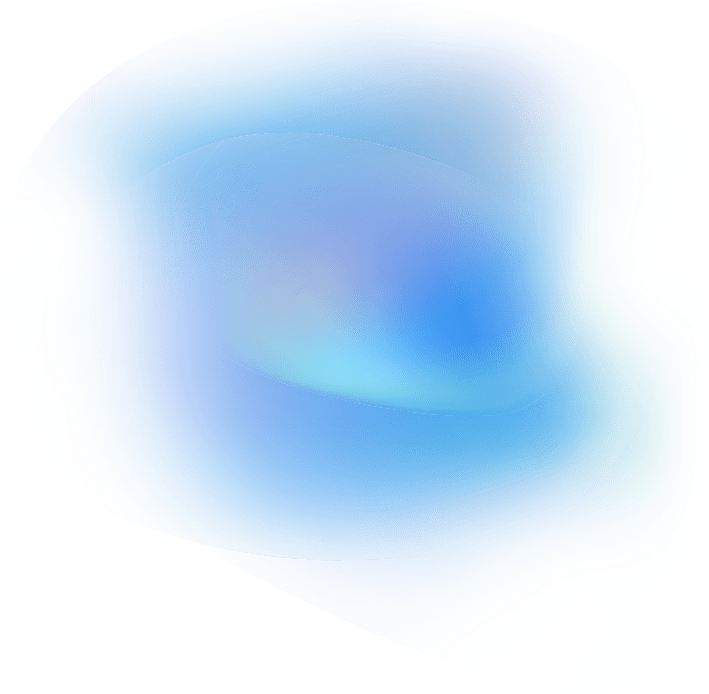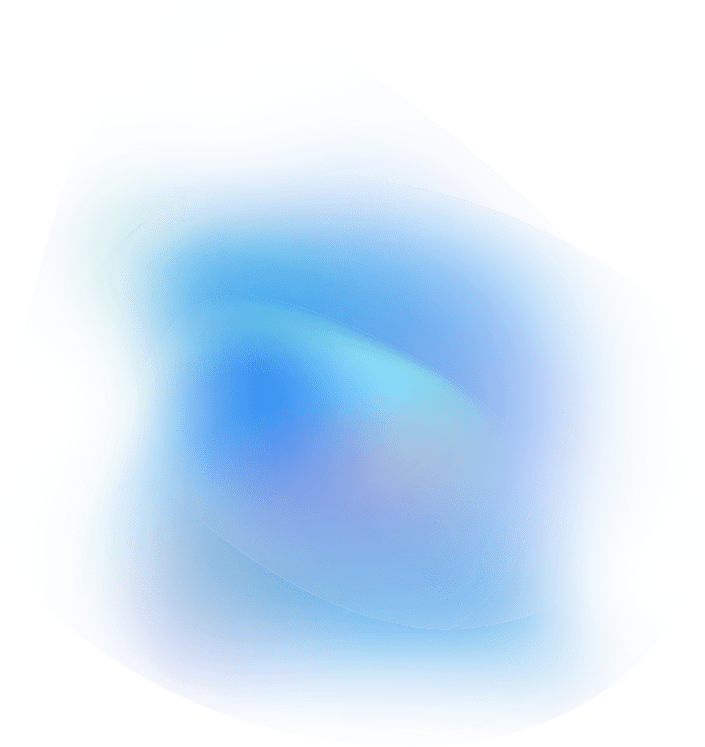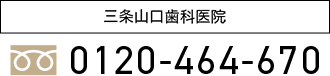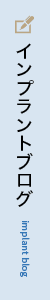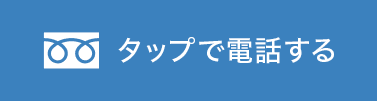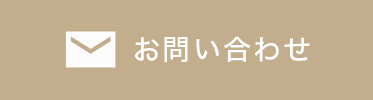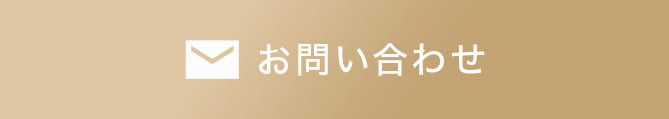インプラントでも歯周病になる?インプラント周囲炎とブルーラジカルについて

インプラントを検討している方のなかには、「インプラントは歯周病にならないの?」 と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、インプラントと歯周病の関係や、歯周病に似た「インプラント周囲炎」について詳しく解説します。
また、当院が導入している歯周病治療器 「ブルーラジカル」 のインプラント周囲炎に対する効果についてもご紹介します。安心してインプラント治療に臨むためにも、ぜひご参考にしてください。
インプラントと歯周病の関係
歯周病はプラーク(歯垢)や、歯石(プラークが石灰化したもの)に付着する細菌によって起こる病気です。細菌が出す毒素により、まず歯肉に炎症が起き、徐々に歯を支える組織が破壊され、最終的には骨が溶けて歯が抜け落ちることもあります。
既に歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルケアやブラッシング指導を受けられた方もいらっしゃると思いますが、予防するには日々のブラッシングと定期的な歯科衛生士によるPMTCが重要です。
実際に、インプラントを希望される方のなかには、歯周病により歯が抜けてしまった、または抜歯が必要になった方が多くいらっしゃいます。歯周病が進行すると、歯周組織や歯槽骨が破壊されていきます。
「インプラントにすると虫歯にも歯周病にもならないのか?」 という質問をよく受けますが、やはりメンテナンスとブラッシングを怠ると歯周病にはなります。これをインプラント周囲炎と言います。
インプラント治療では、歯槽骨にインプラント体を埋入するため、歯周病によって歯槽骨が破壊されていると、治療後の歯の状態に悪影響を及ぼします。また、角化歯肉(歯槽骨に付着する歯肉)の有無も予後に大きく関わってきます。
インプラントは、失った歯を補う治療法として非常に有効です。ただし、歯周病によって歯を失った場合は、治療後の定期検診やメンテナンスをより丁寧に行う必要があります。
悪性度の高い歯周病菌「レッドコンプレックス」が検出される場合は要注意です。
口腔内の細菌を調べる検査機器「orcoa(オルコア)」では、歯周病の進行に深く関わる3種類の悪性菌、いわゆる「レッドコンプレックス」を検出することが可能です。
・Porphyromonas gingivalis (P.g菌)
・Treponema denticola (T.d菌)
・Tannerella forsythensis (T.f菌)
上記の菌は歯周病の重症化に大きく関わっているとされており、現在歯ぐきに炎症がなくても、検出された場合は将来的に歯周病のリスクが高い状態といえます。
レッドコンプレックスが見つかった場合には、ブルーラジカルによる光殺菌治療などが有効とされています。症状が出ていなくても、早めの予防対策を行うことが大切です。
https://dr-yamaguchi-mti.jp/treatment/periodontal/blue-radical/
付着歯肉と歯槽骨がインプラントの予後を左右する理由
歯周組織とは、歯を支えるために欠かせない組織のことです。歯が生えると同時に形成され、付着歯肉、線維組織、そして歯槽骨から構成されています。
歯肉には2種類あることをご存じでしょうか?
ひとつは歯にしっかりとくっついている「付着歯肉(角化歯肉)」、もうひとつは動きやすくやわらかい「可動歯肉」です。
歯周病が進行すると、まず付着歯肉が壊れ、その下にある歯槽骨も徐々に失われていきます。
私は長年インプラント治療を行ってきましたが、歯槽骨は非常に特別な存在だと感じています。なぜなら、同じ条件でインプラントを行っても、付着歯肉や歯槽骨の状態によって、治療後の経過が大きく変わるからです。
付着歯肉がしっかり残っている場合、インプラントは歯槽骨にしっかり埋まり、見た目も自然で、機能的にも安定し、術後のメンテナンスもスムーズになります。
しかし実際には、付着歯肉や歯槽骨が十分に残っている患者さまは非常に少ないのが現状です。多くの方が、歯だけでなく、それを支える歯周組織もすでに失ってしまっているのです。
私は日々の診療の中で、歯肉の重要性を繰り返しお伝えしています。
一度歯周病にかかってしまうと、治療をしても完全にもとの状態に戻すことはできません。しかし、付着歯肉をある程度回復させることは可能です。
だからこそ、歯周病にならないように、日頃の予防がとても大切となります。
インプラント周囲炎とは?
インプラント周囲炎とは、細菌感染によってインプラントのまわりの歯肉や骨に炎症が起きている状態のことです。
日々のブラッシングや歯科医院での定期メンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎のリスクが高まります。インプラントに付着したプラークや歯石内の細菌が原因となり、放置すると歯槽骨が溶け、最終的にインプラントが脱落する可能性があります。
歯周病とインプラント周囲炎は、症状や進行の仕方がよく似ているため、「インプラントでも歯周病になる」 と誤解されがちですが、天然歯とインプラントに付着する歯垢・歯石内の細菌叢や主な原因菌は異なるため、厳密には別の病気として扱われています。
しかし、歯周病の原因菌がインプラント周囲炎の発症リスクを高めることは明らかなため、両者には一定の関連性があります。そのため、歯周病罹患者がインプラントを検討する場合には、インプラント埋入前に歯周病の治療をしっかりと行うことが重要です。
インプラントと歯周病の違いについて、より詳しく知りたい方は次のコラムもあわせてご覧ください。
インプラントと歯周病菌 レッドコンプレックスとは何か
インプラント周囲炎に対するブルーラジカルの有用性
当院では、国が歯周病治療に有効と認めた唯一の医療機器「Blue Radical(ブルーラジカル)」を導入しています。
ブルーラジカルでは、超音波で振動する専用チップによって歯に付着したプラークや歯石を除去していきます。さらに、チップの先端から噴射される3%過酸化水素水に青色レーザーを照射することで、強力な殺菌作用を持つ活性酸素を発生させ、歯周ポケット内の原因菌を殺菌します。
従来、重度の歯周病に対しては外科処置が一般的でしたが、ブルーラジカルは非侵襲的であり、患者さまの身体的負担や精神的不安を大幅に軽減できます。ただし、外科処置とは異なり、歯を支える安定した歯ぐき(角化歯肉)を再生する効果はありません。治療法の選択にあたっては、この点も考慮します。
インプラントを長く安心して使い続けるためには、歯周病やインプラント周囲炎のリスクをしっかりと管理することが欠かせません。
ブルーラジカルは、外科処置に頼らずに歯周病菌やインプラント周囲の細菌を殺菌できる治療機器です。身体への負担が少なく、治療後の安定性を高められる点も大きなメリットです。
ブルーラジカルを導入している歯科医院はまだ少ないのが現状ですが、歯周病やインプラント周囲炎でお悩みの方、ブルーラジカルによる治療を受けたい方は、ぜひ当院にお気軽にご相談ください。
Q1:インプラント周囲炎の予防法は?
A1:日々の丁寧なブラッシングと定期的に歯科医院で検診・メンテナンスを受けることが、インプラント周囲炎の予防につながります。当院では3ヶ月に1回、インプラントに精通する歯科衛生士によるケアを受けていただくことを推奨しております。
Q2:ブルーラジカル治療は、保険適用で受けられますか?
A2:いいえ、自由診療です。治療費は全額自己負担となります。