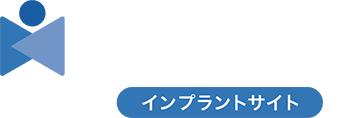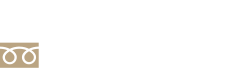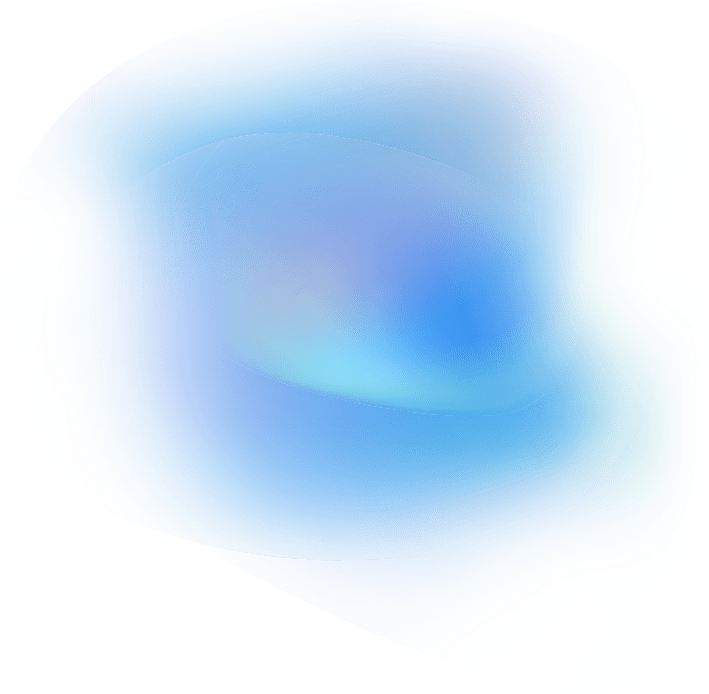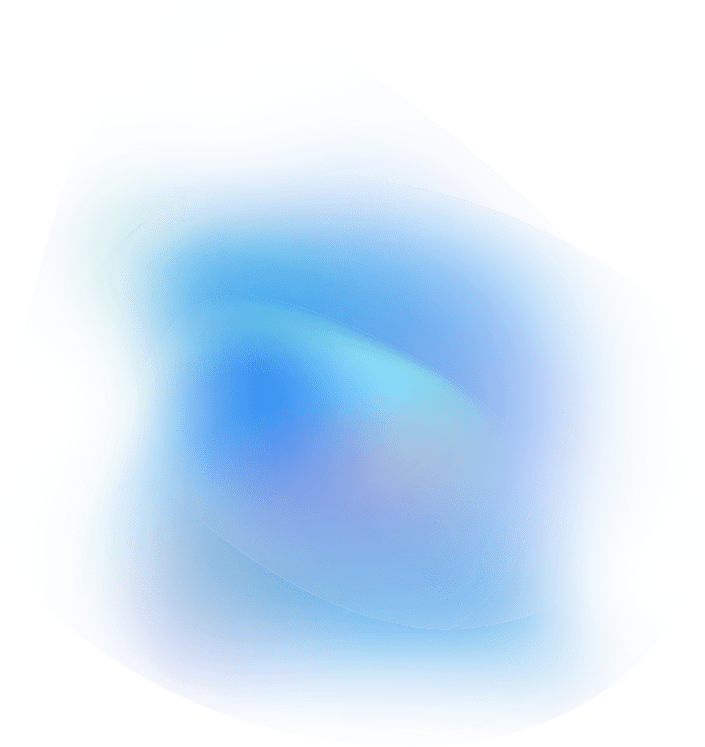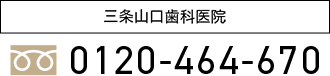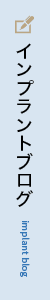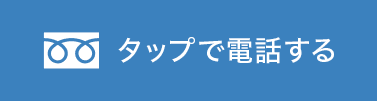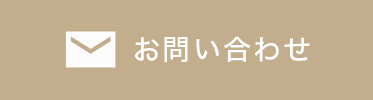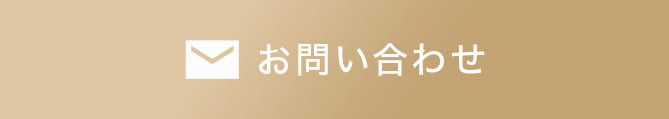インプラントと歯周病菌 レッドコンプレックスとは何か

インプラントを失う原因となるインプラント周囲炎は、歯周病とよく似た経過をたどります。インプラント周囲炎と歯周病の原因となる菌は数十種類にも及びますが、なかでも注意が必要なのは「レッドコンプレックス」と呼ばれる3つの菌です。
歯周病菌やメインテナンスの重要性について正しく理解することで、インプラントの寿命を長持ちさせ、健康的に過ごせるようになります。そこで、本コラムでは、インプラント周囲炎と歯周病の違いやレッドコンプレックス、歯周病菌とがんの関係について詳しく解説します。
歯周病とは?インプラント周囲炎との違い
歯周病は、歯垢(プラーク)内に含まれる細菌が原因で起こる炎症性疾患で、『歯肉炎』と『歯周炎』の2つの段階に分かれます。
初期の『歯肉炎』は歯肉のみに炎症が起こる状態ですが、進行して『歯周炎』になると歯を支える顎の骨が溶け、最終的には歯が脱落することもあります。
インプラント周囲炎も歯周病と同じように進行し、初期段階では「インプラント周囲粘膜炎」と呼ばれますが、さらに悪化すると「インプラント周囲炎」へと移行します。
歯周病とインプラント周囲炎には大きな違いがあります。それは、天然歯には歯と歯槽骨の間に『歯根膜』が存在し、細菌の侵入を防ぐ役割を果たしている点です。しかし、インプラントには歯根膜がないため、防御機能が弱く細菌が直接付着しやすい特徴があります。
このようにインプラント治療後は細菌感染のリスクが高く、炎症が急速に進行しやすいため、適切なケアが欠かせません。
レッドコンプレックスとは?
歯周病の原因となる菌は数十種類にものぼります。そのなかでも、「レッドコンプレックス(最重要歯周病原細菌)」と呼ばれる次の3つの菌が特に病原性が高いことで知られています。
・タンネレラ・フォーサイシア(T.f.菌:Tannerella forsythia)
・トレポネーマ・デンティコーラ(T.d.菌:Treponema denticola)
・ポルフィロモナス・ジンジバリス(P.g.菌:Porphyromonas gingivalis)
いずれも嫌気性細菌(酸素を嫌う性質を持つ細菌)です。この3種類の菌は栄養共生という関係にあり、口腔内に揃うと歯周病のリスクが非常に高まります。それぞれの菌の特徴について解説します。
タンネレラ・フォーサイシア(T.f.菌:Tannerella forsythia)
細長く紡錘状の細菌です。タンパク質を分解する消化酵素「トリプシン」とよく似た強力な酵素を産生し、歯周組織や細胞を破壊します。また、歯周病を引き起こす内毒素も持ち合わせています。難治性の歯周病でよく見られます。
トレポネーマ・デンティコーラ(T.d.菌:Treponema denticola)
らせん状で、運動性を持つ細菌です。歯肉内や血管内に侵入し、タンパク質分解酵素で組織の破壊を進めます。免疫抑制因子も産生するため、白血球などによる貪食を逃れやすいという性質も持ちます。冠動脈や大動脈の動脈硬化を悪化させる菌としても知られています。
ポルフィロモナス・ジンジバリス(P.g.菌:Porphyromonas gingivalis)
細長い円筒状の細菌(桿菌)です。慢性歯周炎の歯周部分に多く存在し、ジンジパインなどのタンパク質分解酵素を分泌して歯周病を進行させます。
口腔内の衛生状態が保たれている間は潜伏していますが、歯周ポケットに出血・潰瘍が生じると、赤血球の鉄分とタンパク質を栄養として高病原性に転じます。さらに細胞を破壊し、免疫系を抑制する硫化水素を産生して、歯周病のリスクを高めます。この硫化水素は、口臭の原因ともなります。
ポルフィロモナス・ジンジバリスは動脈硬化や虚血性脳血管疾患、関節リウマチなどの全身疾患とも深く関わっているといわれており、現在も研究が進められています。
歯周病菌とがんの関係
近年の研究では、歯周病を引き起こす口腔内細菌の一部が『がん』のリスクを高める要因であることが報告されています。代表的なものについて、ご紹介します。
・フゾバクテリウム・ヌクレアタム:口腔がん
・アグリゲイティバクター・アクチノミセテムコミタンス:大腸がん
・ストレプトコッカス・アンギノーサス:大腸がん
・ペプトストレプトコッカス・ストマティス:大腸がん
アメリカでは、歯周病が肺がんのリスクを高めることも報告されています。また、歯周病はがん以外にも次のような病気のリスクを高めます。
・心臓病
・脳血管疾患
・糖尿病
・誤嚥性肺炎
・認知症
長くインプラントを使い続けるためには、治療後のメインテナンスだけでなく、治療前のリスクの確認も重要です。
当院では、インプラント治療をお受けいただく前に患者様の口腔内から歯垢を採取し、PCR検査(Orcoa)でレッドコンプレックス3菌種の量を測定しています。
いずれかの菌量が多い場合は、薬や歯磨き剤・洗口液を処方し、インプラント周囲炎のリスクを最小限に抑えます。さらに、『ブルーラジカル』を導入し、より負担の少ない方法で歯周病原因菌を除去できるよう準備を進めています。
ブルーラジカルについて詳しく知りたい方は、「ブルーラジカルでインプラント周囲炎は新しいステージへ」もあわせてご覧ください。
当院では、インプラント専門医が最新の設備と技術を駆使し、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案しております。治療前のカウンセリングからアフターケアまで、丁寧にサポートいたします。インプラントや歯周病についてお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。お電話またはHP右上のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただけます。
Q1:すでに歯周病と診断されていますが、インプラント治療をすぐに始めることは出来ますか?
A1:いいえ、出来ません。歯周病の治療が終わってから、インプラント治療を開始します。
Q2:歯周病で脱落した歯に対して、インプラントを受けられますか?
A2:はい、歯周病の治療が終わっていることが前提ですが、インプラントを受けることは可能です。ただし、歯周病により顎の骨が溶けてしまっている場合などは、骨造成治療も必要になる可能性があります。
医療法人明貴会 山口歯科医院 理事長山口貴史
歯学博士
日本口腔インプラント学会専門医
国際口腔インプラント学会・ドイツ口腔インプラント学会指導医・専門医
日本抗加齢医学会専門医
高濃度ビタミンC点滴療法認定医
厚生労働省臨床研修指導歯科医